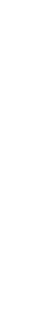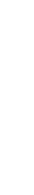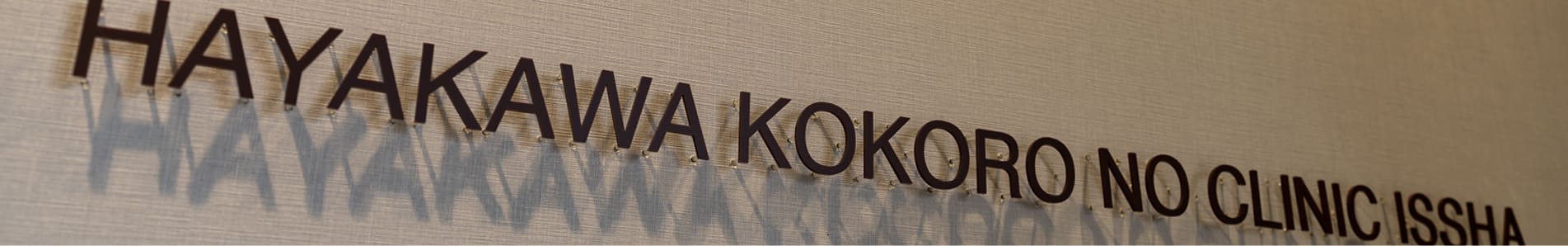
TOPICS
【コラム】療育とは何でしょう?
療育とは何でしょう? ~子どもの特性を生かしたサポート~
療育をお考えの保護者の方へ
「療育」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
けれども、「具体的には何をすることなの?」「うちの子にも必要?」と疑問を持たれる方も多いかもしれません。
療育とは ~基本的な考え方~
療育とは、もともと「治療的な側面」と「教育的な側面」を併せ持つ概念として提唱されたものです。
発達に特性や困難のあるお子さんが、その子らしく成長しやすいように支える関わりや取り組みを指しています。
たとえば、言葉の発達がゆっくりなお子さんや、集団でのやりとりが苦手なお子さんに対して、遊びや日常生活の中で自然に練習できるような環境や支援を整える。
これが療育の基本的な考え方です。
<ADHDのお子さんへの療育的アプローチ>
ADHD(注意欠如・多動症)の場合、特に大切なのは**「特性理解」と「環境調整」**です。
療育で大切にする5つの視点
1.特性の理解:なぜその行動が起こるのかを科学的に理解する
2.環境の工夫:その子が力を発揮しやすい場を整える
3.スキルの習得:生活や学習に役立つ具体的な方法を身につける
4.自己理解の促進:子ども自身が自分の特性を知り、工夫できるようにする
5.周囲の理解:家族・学校・地域が連携して支える
♦具体例:忘れ物が多いお子さんの場合
従来の指導では「忘れないように気をつけなさい」と注意することが中心でした。
しかし療育的なアプローチは少し違います。
・「なぜ忘れるのか」を理解する(例:ワーキングメモリの特性)
・その子に合った補助手段を一緒に探す(例:写真付きチェックリスト、アラーム機能)
・忘れてもリカバリーできる環境を整える
・「忘れやすい自分」を受け入れつつ、工夫する力を育てる
こうした関わりを通して、子どもは「失敗しながらも工夫して乗り越える力」を少しずつ身につけていきます。
療育の現代的な意味 ~「治す」から「支える」へ~
療育は、「特性を治すこと」を目的とするのではありません。
むしろ、その子が自分らしく、幸せに生きていくことを支える包括的な支援です。
早期からの適切な支援により、二次的な困難(自己肯定感の低下、不登校、不安症状など)を予防できることが、研究でも示されています。
小さな「できた!」を積み重ねることで、自己肯定感が育ち、将来の生活や学びの土台となります。
そして、そのプロセスに家族や支援者が寄り添うこと自体が、子どもにとっての大きな力になっていきます。
<当クリニックでできること>
当クリニックでは、発達特性のあるお子さんとご家族を以下のようにサポートしています。
- 発達の評価・診断(必要に応じて心理検査を実施)
- ペアレントトレーニング(保護者向けの具体的な関わり方のアドバイス)
- 栄養面(食事)でのサポート
- 学校との連携(必要に応じて情報共有)
- お薬による治療(必要な場合のみ、慎重に検討)
- 定期的なフォローアップ
<こんな様子が見られたら、ご相談ください>
・じっとしていることが苦手で、常に動き回っている
・忘れ物や失くし物が多い
・順番を待つことが難しい
・集団行動や指示に従うことが苦手
・園や学校で「困っている」と言われた
・子育てに悩み、疲れを感じている
療育を受けることは、決して「できない子」と決めつけることではありません。
お子さんの個性を理解し、その子らしい成長を支えるための、前向きな一歩です。
<よくあるご質問>
Q. 療育はいつから始めればいいですか?
A. 気になった時が始めどきです。早期からの支援ほど効果が高いとされています。
Q. 保険は適用されますか?
A. 診察には健康保険が適用されます。
検査や療育の内容によっては自費となる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
<関連記事>
トピックス一覧へ戻る